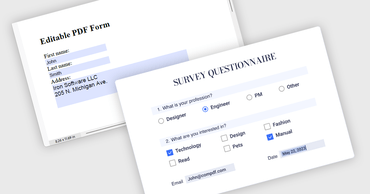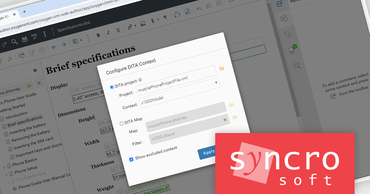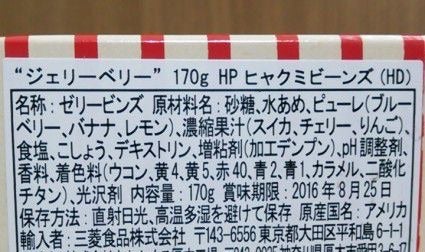↑Composite skeletal reconstruction of Giraffatitan brancai
largely based on paralectotype MB.R.2181 with complete skull MB.R.2223.
Scale bar is 1m for MB.R.2181.
The largest specimen (formerly known as HMN XVII)
is approximately 13% larger than this specimen.
19世紀後半から20世紀前半にかけての古生物学の輝かしい歴史はそのまま帝国主義の一面でもあることについては今さらここに書くまでもないわけで、今であればあらゆる理由で持ち出しがためらわれるような標本が相当数無茶な旅を経て国境を越えたわけである。とはいえ、そうでもなければ永久に人目に付くことなく風化で消えていったであろう標本も多く、このあたりは古生物学にせよ考古学にせよ、今日厄介な問題となっているわけである。
テンダグルといえば東アフリカ随一の恐竜化石(に加えて相当量の浅海の軟体動物化石が産出するのだが)産地であるが、そういうわけでこの丘が陽の目を見たのは1907年、帝政ドイツの植民地時代のことであった。この地で発見された恐竜――ジラファティタンに代表される――は、帝国主義の行く末に至るまで、時代の波に翻弄され続けることになったのである。
ツェツェバエが飛び交いライオンが出ては地元民が襲われるこのうっそうとした、それでいて急峻な丘で最初に恐竜化石が発見されると、にわかにこの地は古生物学者の注目を集めるようになった。探鉱技術者のサトラーによって発見された2種の竜脚類は翌1908年にはそれぞれギガントサウルス・アフリカヌス、ギガントサウルス・ロブストゥスと命名され(すったもんだの末両種はそれぞれディプロドクス亜科のトルニエリア・アフリカーナと真竜脚類――トゥリアサウリアかカマラサウルス一歩手前段階かははっきりしないが、とりあえず以前言われていたようなティタノサウリアではないようだ――のヤネンシア・ロブスタとなった)、そして1909年にはドイツ帝国自然科学界の威信をかけた大規模な遠征隊がテンダグル――タンザニア南部へと乗り込んでいったのだった。
テンダグルの丘の周辺はまさしく化石の山であった。おびただしい数(アルファベットひとつずつの割り当てが追いつかなくなり、かなり訳の分からない整理記号が付けられた)のサイトが開かれ、人力、帆船、蒸気船、汽車を駆使して壮絶な量の化石がベルリンへと送られた。ベルリン大学博物館(後フンボルト大学博物館を経て現ベルリン自然史博物館)の地下収蔵庫が(今もなお)納骨堂のような有様となったのは言うまでもないことで(古くからこの辺の写真はよく知られている)、ヤネンシュらベルリン大の研究者はその後40年以上に渡って――帝政ドイツから共和制ドイツ、ナチスドイツそして東ドイツに至るまでの間、納骨堂に通い詰める羽目になったわけである。
さて、遠征隊の調査は1912年に終わり、とりあえずヤネンシュが手を付けたのが竜脚類であった。遠征前にすでに“ギガントサウルス”2種がテンダグルから知られていたわけだが、他にも複数の新種が存在することは明らかであった。かくして1914年、ヤネンシュはテンダグル層の中部恐竜Middle Dinosaur部層および上部恐竜Upper Dinosaur部層(キンメリッジアン後期~チトニアン;1億5560万~1億4550万年前ごろ)からブラキオサウルス属――モリソン層でただ一つの部分骨格が知られているだけだった――の新種を命名した。恐ろしいことに、遠征隊の旗振り役であったブランカの名を種小名に冠したその恐竜――ブラキオサウルス・ブランカイ――は、実質的に全身の要素が発見されていたのである。
全身の要素が記載されるまでにはその後長い年月を要したのだが、それでもこの発見によってブラキオサウルスの理解は一気に進んだ。1915年には早くも
ブラキオサウルス・アルティソラックスの欠損部の補填にB.ブランカイを用いた骨格図が描かれ(実のところこの時点では
B.ブランカイのほとんどの部位は未記載だったのだが、肩帯や肋骨、尾などはあきらかに
B.ブランカイのそれを参考に描かれており、どうも写真がひっそりとアメリカまで流通していたらしい(一方で頭骨はクリーニングが追い付いていなかったのかあからさまにカマラサウルスである)。ルシタニア号事件が起きたのはこの年のことであった)、雲突くばかりの姿が一般の目に触れるようになったのである。
ベルリンへと持ち帰られたブラキオサウルス・ブランカイのうち、HMN SII(Sサイトで発見された2体目の標本の意。露骨に整理番号である)は全身のかなりの部分が揃っていた。これを基に復元骨格を制作することはすんなり決まった――が、第一次世界大戦とその後のすったもんだを受け、制作は遅れに遅れた。その間に東アフリカはドイツ領からイギリス領へと変わり、テンダグルへ意気揚々とカトラー率いる遠征隊が乗り込み、そしてマラリアの前に斃れた。
1937年、ようやくブラキオサウルス・ブランカイの復元骨格がベルリン大学博物館にお目見えした。変形と損傷の酷かった仙前椎を全て模型に置き換えることで強度面をクリア(頭骨もキャストというか模型が据えられていたことは言うまでもない;長骨は実物だったがドイツ的美意識のためか容赦なく鉄骨が通された)したこの骨格は、当時すでに世界各地で見ることのできたディプロドクスの骨格をはるかに凌ぐ、文字通り「最高」の復元骨格であった。
直後に第二次世界大戦の口火が切られ、復元骨格はあっという間に解体された。ケントロサウルスの化石のほとんどを始め、かなりの数のテンダグル産恐竜化石が空襲で失われたが、ブラキオサウルス・ブランカイの化石のうちのほとんどはどうにか無事であった。気が付いてみればベルリン大学博物館は東側にあり、そしてカトラー隊の命を吸った
大英自然史博物館のテンダグル産ブラキオサウルス類――
今日新種と考えられており“Archbishop”(大主教)の仮称で呼ばれている――も未記載のままかなりのパーツが戦禍に呑まれていたが、それでもヤネンシュは研究を続けたのである。
ヤネンシュのローペースながら(なにしろ研究材料がありすぎる始末である)精力的な研究の甲斐もあり、いつしか(むしろ1915年以降常にというべきか)ブラキオサウルスといえばB.ブランカイという状況ができあがっていた。あらゆるブラキオサウルスの復元のベースとなるのはB.ブランカイであり、模式種たるB.アルティソラックスは半ば忘れられたような状況でさえあったのである。
70年代になり、ジェンセン率いるBYUの調査隊がコロラド南西部で一大産地――ドライ・メサを発見したことで少々状況は変わった。巨大な(実のところ特別巨大でもなかったのだが)ブラキオサウルス類の肩甲骨(や頸椎)がここから産出し、
これの記載にあたって
B.アルティソラックスのホロタイプや同種らしい巨大な断片が取り上げられたのである。
そして80年代になり、骨格図を武器に一躍時の人になったのがポールであった。大英自然史博物館の標本の情報も取り入れ、ヤネンシュが
B.ブランカイの研究の総まとめとして描いた(かなり記号的な)骨格図とはずいぶん趣の違う――まさしくキリンのような――骨格図を
描き出したのである。ポールはここで
B.アルティソラックスと
B.ブランカイの胴椎のプロポーションに著しい違いがあることを指摘し(復元骨格にせよヤネンシュの骨格図にせよ、胴椎の変形の補正は完全に
B.アルティソラックス頼みであった)、
B.ブランカイをブラキオサウルス属の新亜属――ブラキオサウルス・(ジラファティタン)・ブランカイとしたのであった。
ポールの分類は例によって特に相手にされなかったのだが、それ以来、ブラキオサウルスの復元イメージは(B.アルティソラックスも含めて)ポールのジラファティタンに置き換えられることになった。ブラキオサウルスの名のあるところ、ポールに言わせるところのジラファティタンが(皮肉にも)常に立ち続けたわけである。
2007年になり、フンボルト大学博物館改めベルリン自然史博物館のブラキオサウルス・ブランカイのマウントはリニューアルに合わせポールが泣いて喜ぶ姿勢で組み直された。もはや完全に不適切になった胴椎の模型は(頸椎もろとも)取り除かれ、新たに、より適切に作られた模型に差し替えられた。のっぺりした頭も完全な頭骨に基づき拡大された3Dプリントの模型に置き換えられ、足取り高く、前より一層高みから来場者を見下ろす格好となったのである。
状況が変わったのは2009年のことで、
ポール以来初めてまともに(ポールによる比較がまともだったのかはさておき)
B.アルティソラックスと
B.ブランカイの骨学的な比較が行われた。結果、
B.ブランカイを
B.アルティソラックスに特段結び付けられる特徴が実のところ何もないことが明らかになった――ここに、ブラキオサウルス・ブランカイはジラファティタン・ブランカイとして広く認められるようになったのである。
発見から100年以上が過ぎたが、今なおジラファティタンはブラキオサウルス科としては最も完全な骨格が知られているものとなる。ブラキオサウルス科のイメージがいまだにジラファティタンに頼り切りな状況なのは言わずもがなだが、頭骨など、既知のブラキオサウルス科の中では最も「過激」なつくりでもある。
ジラファティタンは相当数がキンメリッジアン後期からチトニアンにかけて海岸付近にのさばっていたらしいのだが、実のところこれは輝かしいブラキオサウルス科の歴史の真ん中あたりでしかない。少なくとも北米では、白亜紀中ごろまでキリンに似た竜脚類の一群が繁栄を続けていたのである。